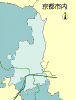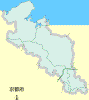通し矢が有名なお堂ですね。
内陣の柱間が三十三間あることから三十三間堂という名前がついているそうで正式な名前は蓮華王院と言います。
平安時代の末期に作られた千体観音堂が唯一残っている所です。
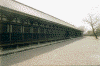

三十三間堂とは道路をはさんで向かい側にあります。
1897年に帝室博物館として発足し、1952年から国立博物館となった歴史を持っています。
いかにも明治時代の建物という雰囲気が漂う本館はフランス・ルネッサンス様式という建築手法で建てられたそうです。

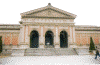

京都国立博物館から少し奥に入った所にある神社で、豊臣秀吉を祀っています。
ここにある銅鐘には「国家安康」と文字を刻んだことから、時の徳川家康が「私の名前"家康"の文字を離して書くとは何事か」と秀吉側に難癖をつけたという逸話があるそうです。


「清水の舞台から飛び降りる」という名言で知らない人はほとんどいないと思います。
東山を代表する寺社の一つになります。
西国33ヶ所巡りの16番札所となっています。
清水の舞台からは京都市内を見渡すことが可能です。
境内の中には音羽の滝や縁結びで有名な地主(じしゅ)神社もあります。




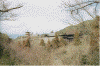
清水寺から高台寺、祇園方面へ向かう途中にある石段の坂です。
ここで転ぶと三年後に死ぬ…なんて話が言い伝えとして引き継がれていますが、実は808年(大同3年)に坂が造られたことから三年坂の名前が付いているとのこと。
また清水寺の中にある子安観音で安産祈願をするために人が通り、その際にお産が安(寧)らかになるように…との願いから産寧坂とも呼ばれるようになったそうです。
写真の方向へ歩いていくと清水寺へ出ます。
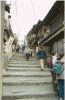
清水寺から高台寺、祇園方面へ向かう途中に産寧坂(三年坂)に続いてある坂です。
産寧坂と同様、ここで転ぶと二年後に死ぬ…なんて話が言い伝えとして引き継がれています。
産寧坂が急な石段なのに対して、二年坂は緩やかなカーブを描く坂となっています。
写真の方向に歩いていくと高台寺方面に出ます。